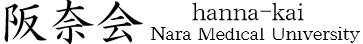阪奈会草創の記
同窓会顧問 川崎 芳春(昭和27年卒)
まえがき
昭和44年5月に誕生した阪奈会は今年で25周年である。大学は開学50周年を迎え、大きく変わろうとしている。(新生)奈良県立医科大学同窓会もいよいよその陣容を整えつつある。
今を去る25年前、母校奈良医大を想う情熱にあふれた同窓諸兄の協力によって、大阪の一角にともされた阪奈会というささやかな灯が、今や大きな燎原の火となって多数の同窓諸兄の心を照らしつつある。大河もその源は一条の流れに過ぎない。千里の道も一歩から始まる。
「継続は力なり」(内村鑑三氏)といわれるが、まさにその通りである。始めはまことに小さな試みであっても、辛抱強く継続することこそ大成への道であるというこの「継続は力なり」の言葉に励まされての出発であった。
いま、わが阪奈会もまもなく設立30周年を迎えようとしている。孔子は「三十にして立つ)」と言ったが、阪奈会はやがてその[而立]の年を迎えようとしている。
設立草創の頃を想い、同窓諸兄がいかに苦労されたか、その軌跡の一端を偲びたいと思う。
会報に見る阪奈会のあゆみ
いま、私の手もとに昭和55年5月21日発行の「阪奈会だより」(発行:阪奈会幹事会、編集: 30年卒辻本 宏)がある。おそらく阪奈会設立10周年に当たる記念すべき会誌であろうと思われる。
この「阪奈会だより」から2人の阪奈会会員の論文を著者のご了解を得て引用させて頂く。阪奈会草創期にご苦労された方々の珠玉のような言葉は、私などがつたない筆で縷縷述べるよりも如何に光り輝いていることか。
(1)阪奈会に寄せる” 原省吾( 昭和29年卒)
「今年も総会が近づいてまいりました。年1回の会合では充分に、その機能を発揮することは困難ではありますが、阪奈会独特の良さもあると思います。
同窓会は同窓会なりに懐古と親睦があり、青春時代の一こまが走馬燈の如く想い出されます。その点では阪奈会は縦の関係と申しましょうか、先輩、後輩、相寄り、別の親しさがあると思います。
先輩は後輩に対して如何に活躍しているか、病院では専門は何であるか、開業医は何処でやっているのであろうかと、新しい情報を知り得ると思います。後輩は先輩の姿をみて、頼もしい一面を知ることが出来ると思います。
夫々に大なり、小なりのメリットはあるのではないでしょうか、唯年1回では少な過ぎる、年2回位は開催したいと思います。
総会以外にクラブ活動、勉強会、大学関係者の講演会等、また、新しいアイデアをもって、やっていきたいと思います。規約にもあります通り、”相互扶助・親睦”は大前提であり、この基本を忘れずに、皆様共々阪奈会を愛して戴こうと思います。・・・以下略」
原先生は相互扶助・親睦という規約の精神を尊重しつつ新しいアイデアを出して、いろいろな活動をしようと呼びかけておられ、情報交換の場としても鋭い目を向けておられる。(現在すでにいろいろの事業がなされていることはご承知の通りであるが、原先生の先見の明に驚く。)
(2)多様化の中の阪奈会” 薄司郎(昭和26年卒)
「最初の卒業生が昭和25年ということで、奈良医大出身医師の数は増え続け、研究畑、そして地域社会の医療に貢献している実地医家の活動を省みるとき、それは既に、近畿一円だけでなく、国家的視野の尺度で評価しても決して過言ではないと考えられます。
同じ大学に6年間、そして同じ職業を選択するという宿命の医大卒業生にとって、同窓意識のより強固な発現は、他の人文科学系学部の同窓生のそれよりも自然な形で、成熟の段階を迎えるのは当然であり、またそうあるべきものと確信しております。・・・略・・・
いまや奈良医大出身者で大阪府内で開業、または府内の医療機関に勤務する阪奈会員諸兄は500余名の多きに達するとのことで、まことに、隔世の感、同慶の至りであります。
・・・略・・・
相互扶助、親睦を第一主義的なものとして創設された阪奈会は、その組織造りや、財源の面でも一段と発展をとげまして、今や、名実ともに高く評価されるに至りました。そしてますます成長を予見されるであろう阪奈会の前途は、必然的に、ある種の「力(パワー)」を生む存在になろうかとも考えられるのであります。
現在、奈良医大同窓会は、やむをえざる状況にあったにせよ、ほとんど無体に等しい存在になりつつあります。(昭和55年当時…筆者/川崎注)あえて私見を申し上げれば、親睦を主目的として発展した会ではありますが、医大同窓会に対する、阪奈会の強力なテコ入れを要する段階にあることを示唆するものであります。・・・以下略」
薄先生は発足後10年にしてすでに「阪奈会は名実ともに高く評価され」て、「阪奈会の前途はますます成長を予見される」と述べておられ、先生の強い自信の程をうかがい知ることができる。
この自身がさらに「奈良医大同窓会に対する、阪奈会の強力な"テコ入れ論”に発展していく。すなわち次の論文である。
(3) ”同窓会再建への対応” 薄 司郎(昭和26年卒)
「阪奈会は基礎的な組織造りを終え、未来のビジョンに想いを馳せるまでに成長致しました。
・・・略・・・
現在の奈良医大同窓会活動は沈滞の方向にあります。(昭和55年当時…筆者川崎注)・・・略・・・
我々阪奈会会員は奈良医大同窓会員であることも厳然たる事実であります。現段階において、機能上自然に共有しうる部分があるならば、同窓会再建に助力を惜しむべきでないと考える次第です。
・・・以下略。
と述べて薄先生は「同窓会再建に阪奈会は助力を惜しむべきでない」と強調されている。薄先生の奈良医大同窓会再建に対する執念とも言うべき情熱は昭和55年当時における阪奈会全会員の情熱でもあったように思われる。
(4) ”阪奈会によせて”・・・”阪奈会を皆んなの手で立派に育てましょう”阪奈会報第6号、
(昭和61年11月発行) 原 省吾( 昭和29年卒)
「・・・略・・・ おこがましいようですが、阪奈会は自分の子供のような気がします。昭和44年発足以来、早や17年の歳月が過ぎ、今や少年期より青年期に入り、心身共に強力な会に育ちました。
‘事業は人なり”と言われます。阪奈会の人材には不足はありません。若い人々の参加と協力を得て、ますますの発展と活躍を心より念じ申し上げます!!」と延べ、昭和60年初期の阪奈会を「心身共に強力な青年」にたとえておられる。さらに原先生は「阪奈会はわが子のよう」との熱い思いの程を吐露されているが、この言葉に私は深い感銘を受けた。阪奈会に対する思いは私も全く同様である。
阪奈会設立は昭和44年5月25日のことであるので、この両先生のご意見は阪奈会発足後10年~10数年後の会員の代表的意見と言える。
設立のいきさつ
木下為弘(26年卒現奈良医大同窓会会長)、原省吾(29年卒)、阿部圭助(29年卒)の各先生と私を含めて4人で阪奈会設立の構想のもとに、大阪府下に広く活動している同窓諸兄に呼びかけたのは昭和44年のことであった。原先生の診療所の1室で設立準備委員会を開き、設立趣意書を発送すべく同窓会名簿と医師会名簿とをたよりに宛名を封筒に書き出したのはすでに深更を過ぎていた。案の定この宛名書きは全く大変な仕事になったが、4人で夜を徹して書いたまだ若かった頃の一夜は生涯忘れることはできない。
初めのうちは4人で阪奈会の将来のことなどそれぞれ語り合いながら、その夢に各々の胸をふくらませて結構たのしく書いていたように思う。しかし夜が更けるにつれて、だんだん疲れてくるし、眠いし、皆黙して語らず、ただただ必死にペンを走らせていたのを覚えている。その当時のわれわれは40才そこそこであったし、すでに青春とは言えないまでも青春の最後の名残でもあったろうか。
あるいは当時すでに「名存実亡」の状態にあった奈良医大同窓会への反省でもあったのか。あくまで相互扶助、親睦をはかることを目的として設立された阪奈会であるが、とても始めから順風満帆の船出という具合にはいかなかった。発足後すぐ直面した難関はもちろんご多分にもれず財政問題である。
当時前記4人がお互いにポケットマネーを出し合って運営していたが、自ずから限度がある。いろいろ討議の末、思いついたのは阪奈会会費の「口座振替による(自動)引き落とし」を大阪府医師信用組合に依頼することであった。このことについてはまず第1に会員の承諾を得ることが先決であるし、第2に大阪府医師信用組合との交渉が必要である。意外な障害にぶつかって難儀したのを覚えているが、それはいまでは考え難いが何と医師信用組合との交渉であった。
主として私が交渉に当たったが組合の担当者はすぐには「うん」と言わなかったのである。
返事はいつも「・・・…..」である。
担当者も「阪奈会? ?」とけげんな顔をしたのは忘れられない。口惜しさで体がふるえ、怒りがこみ上げてきたが、ここでどなっては「水の泡」と黙って辛抱した。そしてねばったあげく、やっと返ってきた答は「少なくとも〇〇万円の定期預金をしてくれたら・・・」という条件づきであった。私は一瞬唖然としたが・・・今は昔のことである。一所懸命阪奈会の実務に尽力されている若い原、阿部両先生にはもうこれ以上無理は言えなかった。黙って私は昭和46年4月20日、木下先生は昭和46年4月23日にお互いに信用組合に〇〇万円の定期預金の手続きをとって始めて阪奈会会費の「口座振替」の一件が決着したのである。
この財政問題が解決して一同ほっとしたのは本音であった。如何なる組織であってもまず第一にクリアしなければならないハードルは財政問題である。言うまでもなく理念は大切であるが、一方実務問題として財政的基盤の確立こそ基本であり焦眉の急務であった。財政問題の決着を契機に阪奈会は第1に公報活動(会報発行)、第2に組織強化活動、第3に事業関係と目標を絞って活動を展開して行った。毎年、重点項目、重点事業を掲げて組織の確立、事業の拡大に尽瘁してきたと言えば言い過ぎであろうか。とくに当時の規約にある当番幹事になられた会員の先生方には毎年の総会開催に際して多大のご努力を頂いた。本誌上を借りて厚く御礼を申し上げたい。
原先生は昭和55年阪奈会名簿の巻頭言に「阪奈会も産声をあげて、早や10数年がたちました。当初は100名にも及ばぬ会でしたが•…·’」と述べられている。因みに平成5 年度総会(平成5年6月26日)庶務報告で、会員数610名と可児副会長より発表されている。しかもこの数字は年々増え続けるはずである。
財政問題も当初の0から平成5年度予算は収入8、318、889円である。まさに隔世の感がある。事業計画も年々多岐に亘っている。名簿整備に始まり、会報発行(年2回)、会員懇親会の開催(学術講演会、保険医療懇談会、医療実地研修会)、会員医療機関連携の積極的対応、厚生部活動の充実、その他である。(このことは阪奈会野崎会長をはじめ役員及び各会員のご努力の賜であって、各位の絶えざる熱意に深甚の敬意を表したい。)
新たなる展開
大阪府医師会の昭和59年度第11回定例理事会(昭和59年5月29日) において、次のような議題が報告されている。
「第36回西日本医科学生総合体育大会が、奈良県立医大を代表主管校として、昭和59年7月20日から9月7日にかけて大阪、奈良、兵庫、和歌山の各地で開催されるが、このほど同大会から本会の後援名義を使用させてほしいとの依頼があったので了承することとしたい。」この理事会報告を当時庶務担当の府医竹中理事から見せられたのは、昭和59年6月、大阪府医師会の郡市区医師会会長連絡協議会の席上である。
この報告も見せられた時、一瞬私は自分の胸を衝かれる思いであった。急逮、奈良医大同窓会強化を計るべしとの天の啓示とも覚えた。大阪府医師会後援とはいえ、「西医体」主管校は奈良医大である。最もバックアップすべき立場にある同窓会の無気力によって母校の後輩に肩身の狭い思いをさせるようなことはできないと思った。この「西医体」問題が契機となって、さらに大学同窓会への阪奈会からの支援が加速することになるのは大方ご承知の通りであると思うのでその詳細は省略する。
むすび
孔子は「吾れ十有五にして学に志す。三十にして立つ。(而立)四十にして惑わず。五十にして天命を知る。(知命)・・・」と述べている。(論語)阪奈会は「而立」の年を迎えんとしていることは前述したが、奈良医大はまさに「知命」の年を迎える。
さらに続けて孔子は「六十にして耳順がう。七十にして心の欲する所に従って、矩を躁えず。」
と論語にいう。
私は齢七十を目前にして「矩を踰えずjという心境には程遠い。
まだまだ未熟者であるがなぜかいま、三国志の英雄曹操(注1) の詠んだ次の詩に心がひかれるのである。
老驥、櫪に伏すも 老驥伏櫪(注2)
志、千里に在り。 志在千里
烈士、暮年、 烈士暮年(注3)
壮心、巳まず。 壮心不巳
年老いてなお、壮心つまり、やらんかなの意欲だけは持ち続けたいという曹操の思いに古希を控えてなおこだわり続けている私である。
「継続は力なり」(内村鑑三)といい、また「壮心巳まず」(曹操)という言葉こそ、開学50周年を迎えた奈良医大にこそふさわしいと思う。
県、大学の努力でいま奈良医大は面目を一新しつつある。「継続は力なり」であり、「壮心己ま丸の気概を持って、知命の年を迎えたいまこそ名実ともに国公立医科大学の雄として、辻井学長を中心に今後の大いなる発展を期待して止まない。
注1 三国の魏の始祖、人も知る三国志の英雄。権謀に富み、詩をよくした。
注2 一日に千里も走るといわれる名馬。「櫪」馬屋の意。
注3 晩年。
阪奈会 可児 敏紀(昭和43年卒)
阪奈会は昭和44年に奈良医大卒業で、大阪地区にて開業している先生方が合い寄り、ゴルフ、学術講演会などの親睦団体として発足したと聞き及んでおります。その頃になりますと地区医師会にて理事などの役員になられて、府医にも顔を出すと昔懐かしい顔に会えたのがこの会を作る1つのきっかけになったと話されているのを聞いております。その当時、原省吾先生、阿部圭助先生、木下為弘先生、川崎芳春先生方が中心となり、この会を引っ張って行かれました。私も1、2度講演会にも出席
させて頂くようになり、その当時はまだ大学医局に在籍しておりましたので、1年に1度顔を合わせにいくうちに互いに屈託のない学生当時の話に花が咲いているのを懐かしく聞かせて頂いておりました。
その後、原先生等から阪奈会会員も増加してきたこともあり、更なる発展のため、開業医のみでなく、広く勤務医の先生方にも参加して頂いて活動してはどうかとの意見があり、会則を変更して1団体になるよう努力し、昭和60年に昭和31年卒業の野崎瞭ー先生が会長に就任され、現在下記の役員にて活動しております。阪奈会会員は600名以上で、そのうち240数名の先生方が毎年変動がありますが会費を納入して頂いております。
大阪府医師会は56地区あり、現在各地区にて60数名の先生が役員としてご活動され、会長や副会長の重責も担っておられます。
当会の活動として、講演会、懇親会(会員家族、従業員を含む)、医療談話会などにて各方面からの情報を提供出来るよう努力し、会員各位に少しでも役に立った企画を行っております。また、ゴルフ、テニスの部会をつくり、心身ともに有意義な会に持っていくよう鋭意努力しております。
大学同窓会あっての阪奈会であり、当会にても出来るだけの助力を奈良医大の発展に寄与できればと思い、筆を置きます。
阪奈会役員
会長 野崎 瞭ー(31年卒)
副会長 寺西 範年(36年卒) 可児 敏紀(43年卒)
理 事 吉村 隆司(35年卒) 三橋 二良(36年卒)
村上 叡(37年卒) 吉矢 久人(39年卒)
新井 幸吉(42年卒) 北中 登ー(42年卒)
津川 善彦(44年卒) 市川 政裕(49年卒)
細井 祐司(50年卒)
議 長 川崎 芳春(27年卒)
副議長 神末 光隆(33年卒)
監事 原 省吾(29年卒) 吉岡 諄二(29年卒)
“阪奈会だより’’阪奈会保険医療懇談会 寺西 範年
平成2年3月社会保険診療報酬改定の概要が発表された直後に、この改定の要旨も含めて難解なる保険医療を十分に把握し、今後の在阪奈良医大同窓生のより有益な診療体制ができるように、阪奈会・保険医療懇談会が昨年に引き続き開催された。
日 時 平成2年3月11日(日)午後3時より
午後6時より 懇談会
場所 大阪市都島区大閤園
懇談会話題
1、社会保険診療報酬改定内容の理解とその活用
2、社会保険診療審査の現況
3、実例レセプトにおける審査委員の分析と意見
疑義質問(過誤調整問題・薬効の解釈など)
在阪同窓生に、社保・国保・労災と併せて12名の審査委員がおられ、審査委員諸先生を囲んでの保険医療研修会であった。
活発な質問に適切な解釈・解答が加えられ、特に原省吾先生提出の冊子・社会保険診療審査の現況の説明に改めて保険医療の難しさを認識し、大阪では緊急の課題ともされている過誤調整問題(保険者再審)についても突っ込んだ意見交換がみられた。
その収入のほとんどが保険診療から得られている現況としては、それがいかに歪んだものであっても診療報酬規程枠外に立てる術もなく、正しい解釈に基づいた保険医療を行うべきであろう。
4 名奈会より同窓会再建に期待して 馬嶋 保(昭和27年卒)
昭和40年代後半、名古屋市、大垣市在住の本学卒業生有志が集まり、愛知・岐阜。三重・静岡県を含む東海地区同窓会を『名奈会』と名付け、折りにふれて会合をもっている。
現在会員数は、本年7月確認できたもの–愛知県37名・岐阜県11名・三重県24名・静岡県4名、計76名–。
恩師佐藤寿昌•吉田邦男・神谷貞義各先生も地元に在住しておられる。名奈会同窓生も大学教授・助教授・講師・国公立病院院長・副院長、市民病院級の大病院理事長、医師会会長・副会長、各分科会理事等々に多士済々、各分野に地元大学卒業生に優るとも劣らない活躍をしている。
5 京奈会だより 宮下 義郎(昭和28年卒)
近年京都地区でも同窓生が著しく増加してきたので、地区同窓会的性格の会を創設したいという機運が、浦川(28年卒)、松田(29年卒)、宮下らの間でたかまってきたのが奇しくも同じ頃であった。
この3名が発起人となって準備をすすめ、59年10月下旬に奈良県立医大京都府人の会を開催し、約20名が出席した。席上発起人を中心に同窓会委員の相互親睦と研鑽を目的とする会の必要性が強調され、会則も略々定まって、名称を京奈会とし、毎年11月第3日曜日に定例総会を開く事を決定した。60年度総会は滋賀県も含めて、90名の同窓生に案内状を発送し、11月17日に開催した。出席は20名でやや淋しかったが、総会後、法医学廣田教授の研修講演を拝聴し、懇親会でははるばる馳せ参じられた吉本同窓会長の挨拶もあり、一同和気あいあい、盛会そのものであった。
今年も京都の山々が錦秋を帯びる頃、京奈会が益々盛大に有意義に開かれることを念願してやまない。